雪が解け、草木が芽吹き、うららかな日差しの射す春も終わりに近づく頃・・・
田植の準備が始まり、畑では種まきが行われます。

ちょうどこの頃、二十四節気では穀雨の季節を迎えます。
まだ日本が農耕中心だった時代にも、穀雨の季節になると、田植の準備が行われていました。
この辺りが、節気の名称に「穀」の字が使われている所以なのかもしれません。
そんな思いを抱きつつ、穀雨の持つ意味を紐解いていこうと思います。
穀雨の日と期間や、七十二候が表している穀雨の季節も併せてお届けいたします。
穀雨の意味とは?
穀雨という文字を見て、「穀」は穀物、「雨」は降り注ぐ雨を指しているということは想像がつくかと思います。
穀物に雨が降り注ぐから穀雨???というかすかな期待を持って、こよみ便覧を見てみましょう。 ⇒ 「こよみ便覧」 ※コマ番号「7」で、実際の記載を見ることができます。
「春雨ふりて百穀と生化すればなり」
穀雨の欄には、このような記載があります。
ここで解りにくい言葉を拾うと、「百穀」と「生化」でしょうか?
まず「百穀」ですが、ここでの「百」は数量ではなく、数が多いことを表しています。
百穀でたくさんの穀物、すなわちさまざまな穀物という意味です。
そして「生化」ですが、こういう熟語は調べても出てきませんでした。
「生」は生まれるという想像がつきますが、問題なのは「化」の意味です。
頭の中にあるのは、「ばける」とか「かわる」なのですが、これではつじつまが合いません。
調べてみたところ、自然が万物を育てる働きという意味がありました。
こうなると生は「生まれる」ではなく、生えると解釈した方がしっくりきます。
ここまでの事を合わせて、こよみ便覧にある言葉の意味をまとめると、
「春雨が降り、さまざまな穀物が生え育つ時期だから(穀雨)である」
となります。
もう少しかみ砕くと、
「春雨が降ることで、さまざまな穀物が芽を出し成長する時期だから(穀雨)である」
と解釈することができます。
これは、言葉の意味から独自に解釈したものですが、一般的には「百穀を潤す春に降る雨」を穀雨というとされています。
ちなみに・・・
この頃に降る梅雨のような長雨のことを、「菜種梅雨」と呼んでいます。

ちょうど菜の花が咲く頃なので、こう呼ばれるようになりました。
穀雨の日と期間 2025年はいつ?
作物の成長を促すありがたい春の雨!
そんな雨の日が多くなってくる穀雨の季節とは、いったい、いつごろ訪れるのでしょうか。
旧暦3月後半の節気にあたる穀雨は、毎年4月20日頃に訪れます。
また、穀雨の日から次の節気である立夏の日の前日までの期間を穀雨と呼ぶ場合もあります。
2025(令和7)年はいつかというと、穀雨の日は4月20日、その期間は4月20日~5月4日です。
穀雨の季節
さて、穀雨の持つ意味とその時期が解ったところで、穀雨とはどんな季節なのか?を、七十二候の言葉を借りて見ていきたいと思います。
七十二候では、穀雨の季節を「初候・次候・末候」の3つ分けて、より解りやすい言葉で季節を表しています。
それでは、初候から順にどうぞ^ ^
穀雨 初候 葭始生
「葭始生(あしはじめてしょうず)」
水辺の葭に、若芽が芽吹く季節を表しています。

葭は、葦のことです。
古くには、日本の湿地帯を葦が覆っていました。
古事記や日本書紀においては、日本のことを「豊葦原瑞穂国」と呼んでいるほどです。
この頃は、瑞穂(みずみずしい稲穂)に負けず劣らず、青々と茂る葦が草原のように広がっていたのかもしれません。
そんな、風景を青芝と呼んだそうです。
きっと、葦の群生している姿を、芝草の続く平原になぞらえたのでしょう。
葦という名前は、青芝が変化したものと言われています。
また、「あし」は「よし」とも呼ばれます。
これは、「あし」が、悪(あ)しに通じると考えられるようになり、それを避けるためによ(良)しと呼ぶようになったという事です。
葦ってなに???と、思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、葦の群生を見ることが出来る地域は、限られてきています。
でも、夏になると、簾を見かける事はありませんか?

エコブームが訪れてからというもの、日本に古くからある簾が、日除けとして見直されてきました。
その材料になっているのが、他でもない葦です。
簾にはいくつかの種類がありますが、中でも「葦簀」と呼ばれるものは、葦だけで作られており、涼しさにも違いがあるそうです。
穀雨 次候 霜止出苗
「霜止出苗(しもやみてなえいずる)」 ※「しもやんでなえいずる」とも読ませます。
霜が降りなくなり、苗代で稲の苗が成長する季節を表しています。

この頃から、日差しは徐々に強くなり、夏へと向かいます。
田植の準備が始まるのも、この頃です。
突然ですが、草餅はお好きですか?
緑色をしたお餅なのですが・・・

中に餡を包んで、大福にもなっていたりします。
もしかしたら、草大福の方がお馴染みかもしれません。
どちらにも「草」とついていますが、その「草」が蓬です。 ※過去には母子草を使っていたこともありますが、現在は蓬が一般的になっています。
草大福などは、和菓子屋さんなどで一年中お目にかかることができるので、季節感はあまり無いかもしれません。
でも、江戸時代の頃には、ちょうどこの時期に出始める蓬の若葉を使って草餅を作っていました。
穀雨 末候 牡丹華
「牡丹華(ぼたんはなさく)」
牡丹が、大きな花を咲かせる季節を表しています。

大振りでとても美しい花を咲かせる牡丹は、花王とも呼ばれ、日本でも古くから栽培されてきました。
原産地は中国で、日本に入ってきたのは、奈良時代(天武天皇治世の頃)と言われています。
そもそも、薬用として渡来したもので、観賞用として広まったのは江戸時代のことです。
もしかしたら、牡丹が薬になるということは、ピンと来ないかもしれません。
薬として利用されるのは、牡丹の花ではなく根の皮です。
牡丹の根の皮を乾燥させたものを牡丹皮といい、現在も生薬として利用されています。
牡丹といえば・・・ 「立てば芍薬座れば牡丹 歩く姿は百合の花」という諺があります。
美しい人を表す言葉としてご存じかと思いますが、元々は生薬の用い方をたとえたものなのだそうです。
このことを、もう少し詳しく知りたい場合は、こちらのサイトをご覧ください。 ⇒ 「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」
最後に・・・
さてさて、春と言えばやっぱり桜!という方が多いかと思いますが、古くからある春祭りが行われる地域も少なくありません。
穀雨の季節は、ちょうど春祭りが行われる時期でもあります。
寒い冬を乗り越え春を迎えた事を喜ぶと共に、秋の豊作を祈って行われるのが春祭りです。
祭りを楽しむだけではなく、時には、遠い昔に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
その歴史や由来を知ることで、いつもの祭が、また違ったものに見えてくるかもしれません。
≪参考≫ 4月20日、二十四節気「穀雨(こくう)」の意味と季節の楽しみ / tenki.jp 日本気象協会 「簾(すだれ)と「葦簀(よしず)」の違い / 違いがわかる事典 株式会社ルックバイス びお・七十二候 / 町の工務店ネット 立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花 / 北海道立衛生研究所薬草園 林 隆章


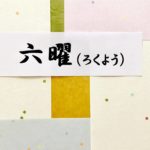
コメント