二十四節気は、一年を24の節気に分けたもので、古くから季節の移り変わりを知るすべとして利用されてきました。
簡単に説明すると、春分・秋分・夏至・冬至を起点とし、起点から起点までをそれぞれ6つの節気に分けたものになります。
詳しい説明は、こちらの記事をご覧いただくことして・・・
季節は春!
二十四節気の春は、立春から始まります。
突然ですが、質問です。
次の季節(夏)が始まる立夏までの間にある、春を表す節気をいくつご存じでしょうか?
えぇーーーーーっ!! そんな事、急に言われても・・・???!!
という声が聞こえてきそうですが、そんなあなたも「立春」や「春分」はきっとご存じのことでしょう。
残る4つの節気は「雨水・啓蟄・清明・穀雨」です。
もしかしたら、テレビやラジオで聞き覚えのある節気があるのではないでしょうか。
これらの節気を、訪れる順に並べると「立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨」となります。
さぁて・・・前置きがあまり長過ぎてもいけませんm(_ _)m
今回は、春を表す節気の中から「清明」についてお届け致します。
勝手な思い込みかもしれませんが、もしかして清明はご存じの無い方が少ないかな?と思うところもあり、春の節気だよぉ~というところだけを、先に書かせていただきました。
それでは、清明とはどんな日を表しているのか?その意味からみていきましょう。
二十四節気 清明の意味とは?
清く明らかと書く「清明」は、「せいめい」と読みます。
二十四節気において、どんな日を清明と呼んだのか?こよみ便覧の記載を見てみると
「万物はつして清浄明潔なれバ此芽ハ何の草と志る也」
とあります。
もう少し読みやすくすると「万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草と志る也」となります。 ※実際の記載を確認したい方は、こちらへどうぞ! ⇒ 「こよみ便覧」 二十四節気の記載は、コマ番号「7」にあります。
清明は「清浄明潔」を略したもので、清浄明潔は「万物ここに至って皆潔斎なり」と称されます。
なんだか、ややこしいですね^ ^;
「万物ここに至って皆潔斎なり」は、「この時期は、万物がすべて明るく清らかである」と言い換えることで解りやすくなるかと思います。
そして、ここでの「万物」は「さまざまな物」ではなくさまざまな草木と訳します。すると「発する」は芽吹くという想像がつくのではないでしょうか。
まとめると、「様々な草木が芽吹き、すべてが明るく清らかで、この芽が何の草か解るようになるから(清明というの)である」となります。
うーん・・・これでもまだ、どこかスッキリしない感じがしませんか?
柔らかい日が降り注ぎ、空気も澄んでいる春は、様々な草木が芽吹き成長を始める時期です。

先にもあるように、芽吹くことで草木の種類が解るようにもなります。
「雪が解け、うららかな日差しの射す中、長い冬を耐え忍んできた草木が芽吹き、様々な花が咲き始める」
そんな清々しく生き生きとした季節を形容して清明と呼んだのではないかな?というのは、個人的な解釈です。
二十四節気 清明はどんな季節なの?
ここからは、清明という季節を、七十二候の言葉を借りてみていきたいと思います。
七十二候では、一つの節気を初侯・次候・末候の三つに分け、より身近な言葉で季節を表しています。
清明 初候 玄鳥至
「玄鳥至(つばめきたる)」
寒い季節を南国で過ごしていツバメが、日本に帰ってくる季節を表しています。

玄鳥は、ツバメの異名です。 至(る)には、その場所に行きつくとか到着するという意味があります。
ツバメは、古くから身近に存在してきた野鳥です。
その昔、まだ農薬が無かった時代には、作物を荒らさずに害虫を食べてくれる鳥として大切に扱われていました。
なぜかというと、ツバメは飛んでいる虫を空中で捕まえて餌とするため、田畑を荒らすことが無かったからです。
そういうことがあったからなのでしょうか?
- ツバメが巣をかけた家は縁起がいい
- ツバメは火事を出す家には巣づくりしない
- ツバメが三度巣をかけると千万長者になる
などなど、ツバメの巣を縁起物とする言い伝えが多く残っています。
そういえば、民家の軒下にあるツバメの巣からひな鳥が顔を出して親鳥を待っているという風景も、以前はそう珍しいものでは無かったように感じます。
もともとは野鳥のツバメが、民家の軒下などに巣をかけるようになったのは、カラスや蛇などの猛禽類からヒナを護るための知恵というのが一般的な説です。
清明 次候 鴻雁北
「鴻雁北(こうがんかえる)」 ※「こうがんきたす」、「がんきたへかえる」とも読みます。
日本で冬を過ごした雁が、北へ帰る季節を表しています。

夏鳥のツバメと入れ替わるように、冬鳥の雁が旅立っていく季節です。
雁は、乱獲による減少のため現在は保護対象の鳥となっていますが、かつては人間と深いつながりがありました。
その証拠と言ってはなんですが・・・
雁は冬の季語になっていますし、小説や映画にも登場しています。
また、家紋にも雁をかたどったものがあり、そのような家紋を総称して「雁金」と呼んでいます。
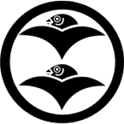
有名どころをあげるとすると、戦国武将の柴田勝家が用いていた「二つ雁金」でしょうか。
ちなみに、「鴻雁北」は、寒露初候の「鴻雁来(こうがんきたる)」と対になっています。
清明 末候 虹始見
「虹始見(にじはじめてあらわる)」
雨の後、虹が見えるようになる季節を表しています。

雨上がりに虹を見つけると、嬉しくなるというかなんというか、なんとなく得をしたような気持ちになったりもするものですが・・・
春になって初めて見る虹を、初虹というそうです。
変わりますが、「春告げ魚」と呼ばれる魚をご存じでしょうか?
北国での春告げ魚は、元々「鰊」を指していたものですが、漁獲量が減少したこともあり、現在では「メバル」がそう呼ばれています。
関西地方での春告げ魚は「鰆」です。
春告げ魚は、地域によって違いはありますが、メバルも鰆も、この頃から旬の時期を迎えます。
あれ?鰆って冬が旬じゃないの?と思った方もいらっしゃるかと思いますが、これは地域性の違いとしか言いようがありませんm(_ _)m
春、産卵のために集まってきた鰆は、卵や白子もおいしくいただくことができます。
さらにもう一つ!鰹が旬の時期を迎えるのもこの頃からです。
鰹は「初鰹」と「戻り鰹」と旬の時期が2回ありますが、この季節の鰹は「初鰹」と呼ばれています。
2026年の清明はいつ?
春がいよいよ本格化する清明は、旧暦3月の節気になります。
清明が訪れる日、もしくはその日から次の節気である穀雨の前日までの期間を指して清明と呼ぶこともあります。
新暦での清明は、毎年4月5日頃に訪れ、その期間は4月20日頃までとなります。
2026(令和8)年は?というと・・・
清明の日は4月5日、その期間は4月5日~4月19日迄となっており、2025年より1日短くなっています。
最後に・・・
この記事を書きながら、「旬」という感覚が薄れてきているかも?と感じていました。
魚や野菜はもちろんのこと、お花で季節を感じるということも少なくなって来ていると思いませんか?
季節に関係なく様々なものが手に入るのは嬉しい事でもあるのですが、季節感が無いのも寂しいなぁと・・・
《参考》
二十四節気 清明 / 不変山 永寿院
誰もが知るツバメの、誰も知らない名前の由来って?七十二候「玄鳥至(げんちょうきたる)」/ tenki.jp
雁(がん、かり)の生態について。 / 動物JP
春告げ魚 / 日々是活き生き-暮らし歳時記
「虹始見」雨上がりに見える春の知らせ|七十二候ダイアリー / ROOMIE
カツオ/鰹/かつお:生態や特徴と産地と旬 / 旬の食材大百科
清明 / 二十四節気 日本の行事・暦
旧暦で楽しむ日本の四季~二十四節気と七十二候~ / 別冊宝島編集部編
現代こよみ読み解き事典 / 岡田喜朗・阿久根末忠編著




コメント