12月といえば・・・
真っ先に思い浮かぶのは、クリスマスでしょうか。
それ以外にも、忘年会があったり、正月を迎えるための大掃除をしなくてはいけなかったりで、何かと気ぜわしい時期かと思いますが、お歳暮を贈るのもこの時期になります。
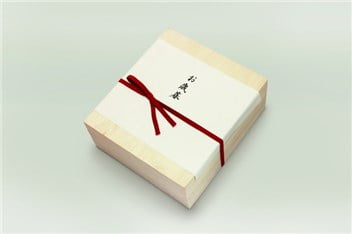
今年1年お世話になった方へ感謝の気持ちを届ける「お歳暮」は、忙しさに紛れて忘れないようにしたいものです。
お歳暮の意味と由来
いい機会なので、お歳暮の意味や由来について軽く触れたいと思います。
お歳暮と聞くと、年末にいただく贈り物を思い浮かべるように、今では贈答品そのものを指す言葉となっています。
が・・・
「歳暮」は、元々「歳」の「暮れ」、つまり「年末」を表す言葉として用いられていました。
お歳暮の由来は?
古来日本では、新年に年神様にお供えするものを年末のうちに贈る(配る)という風習がありました。
中でも、お供えものを年の暮れに実家や本家に持ちよる行事をお歳暮と呼んでいました。
当時のお供え物は、塩鮭や数の子、餅などの食料品が主であったのですが、これは年神様に供える「お神酒」の酒肴に由来していると言われています。
今のスタイルは江戸時代から始まった!
お歳暮に「感謝の気持ちを込めて贈る」という行為が生れたのは、江戸時代になります。
江戸時代の商品の売買は、掛売りで行われるのが一般的でした。
「ツケで買う」と言えば解りやすいでしょうか。
ツケの清算が、半年(もしくは1年)に1度だったため、支払いをする年末に、日頃の感謝とお礼を込めたお歳暮として贈り物を渡していたそうです。
他にも、自分が住んでいる長屋の大家さんには、日頃のお礼と来年もまたよろしくお願いしますという気持ちを込めて、贈り物を持参しました。
これらのことが元々の風習とあいまって、年の暮れに日頃のお礼と感謝の気持ちを込めて贈る贈り物としてのお歳暮が定着していきました。
お歳暮は誰に贈ればいいの?
お歳暮は、日頃お世話になっている人やお世話になったけれど普段なかなか会えない人などに、感謝の気持ちを込めて贈るものです。
そして、必ず誰かに贈らなければいけないという決まりごとはありません。
一般的な送り先は、
- 両親
- 義父母
- 仲人
- 親戚、兄弟姉妹
- 友人、知人
- 上司
- 会社関係
などです。
お子様がいて、習い事をしている場合はその先生に贈る場合もあるようですが、学校の先生に贈る必要はありません。
また、結婚が決まっているカップルの場合、それぞれの実家同士が贈りあうこともあります。
注意が必要なのは、会社の上司へ贈る場合です。
上司への贈り物を禁止している会社もありますので、前もって確認しておきましょう。
お歳暮を贈る時期はいつ?
お歳暮は、季節の挨拶ですから、贈るタイミングをはずさないようにしましょう。
本来ですとお歳暮を送る時期は、お正月の準備を始める「事始めの日」にあたる12月13日~12月20日までになります。
ただ近年は贈り始める時期が早くなっており、11月末頃に(12月に入ると届くように)贈るという方も多いようです。
地域による習慣の違いをあげると、
- 関東では12月初旬~12月31日
- 関西では12月13日~12月31日
とされていますが、年末が押し迫った忙しい時期に届いては迷惑ということもありますので、12月20日頃までに届くように贈るのが無難です。
やっちゃった!年内に間に合わない(T T)と言う場合
もし、うっかり時期を逃してしまった場合は、
- 関東地方であれば1月7日(松の内)
- 関西地方であれば1月15日
まで届くように、のしの表書きを「御年賀」として贈ります。
これ以上に遅くなってしまった場合は、松の内を過ぎてから2月4日頃(立春)までの間に、「寒中御見舞い」や「寒中お伺」として贈ってください。
最後に・・・
ここでは、お歳暮はいつからいつまでに贈るものなのか?その期間だけについて書きましたが、実際問題!
- お歳暮は何がいいのかな?
- いくら位の物がいいんだろう?
- お歳暮を贈る時の決まり事ってあるのかしら?
などなど、頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。
そのあたりを含めたお歳暮のマナーや、こんな時はどうしたらいいの?といったよくある疑問については、それぞれ記事を改めています。
お手数ではありますが、記事右上にある検索窓に「お歳暮」と入力して、ご希望の記事を選択していご覧ただければと思います。
≪参考≫ お中元とお歳暮 / 日本文化いろは事典 お歳暮を贈ろう / AllAbout おせいぼ【お歳暮】 / 冠婚葬祭マナー&ビジネス知識




コメント
お歳暮をおくる予定にしてた親戚や知人の方々に訃報があった場合はお歳暮はNGでしょうか? またそれ以降はどの様に対処すれば宜しいでしょうか?
藤井さん
こんばんは。
ご質問についてですが、「お歳暮のマナーQ&A」の記事が参考になるかと思います。
以下、同様の内容になりますが、記載いたします。
お歳暮の送り先が喪中の場合でも、お歳暮を贈ることは失礼にあたりません。
ただ、四十九日前であったり、先方が気落ちしているという場合は、時期をずらして送るといいでしょう。
この時ののしは「寒中見舞い」「寒中お伺い」となります。
また、「お歳暮」や「寒中見舞い」という表書きは書かずに「無地のし」または「粗品」として贈る方法もあります。
ご参考になれば、幸いです。